
眼振と捻転斜傾(前庭障害)
前庭障害とは
眼振と捻転斜頸の二つを特徴とする神経徴候を前庭障害といいます。
バランスを司る前庭系の異常により引き起こされる神経徴候です。5分前に見た時は元気だったのに、次見た時には眼が揺れ始めて(眼振)首を傾げる(捻転斜頸)ような姿勢になっていて驚いた、と言った経験はありますでしょうか?このくらい急性発症するのも特徴です。千鳥足(運動失調)になる、すぐに倒れる、壁つたいに歩く、その場でグルグル回るなど歩き方にも異常が出ることが特徴的です。
前庭は末梢性と中枢性に分かれ、どちらに病変があるかで治療プランも大きく変わることも少なくありません。炎症、腫瘍(腫瘤)、外傷、梗塞、特定の栄養欠乏(代謝性)、レアではありますが内分泌(いわゆるホルモン)疾患が原因になることもあります。高齢犬/猫ですと、MRIを撮っても原因となりうる所見が得られない特発性前庭障害にもよく遭遇します。
捻転斜頸と眼振→前庭障害
運動失調、旋回、ウォールウォーク、ジャンプできない
原因は大きく中枢性と末梢性に分かれる
診断と検査プラン
診断及び検査はまずは神経学的検査、耳道及び鼓膜の確認、レントゲン、各血液検査から始めます。これらを確認することで、他の神経徴候が無いかどうかと明らかな病変があるかが分かります。最終的な診断はMRIになることが多いです。もし麻酔のリスクが高いなら試験的治療で経過を見る手段もしばしば選択しています。
中枢性だった場合、他の神経徴候も併発していることが多いです。その場合はかなり緊急性が高いです。一方末梢性の場合、特に何をしなくても改善する症例もいれば、治療をしっかり実施しないと治癒しないことも多いです。この判断はご自宅では困難であると予想されますので、前庭障害を疑う場合は早めの受診を推奨します。
投稿者プロフィール









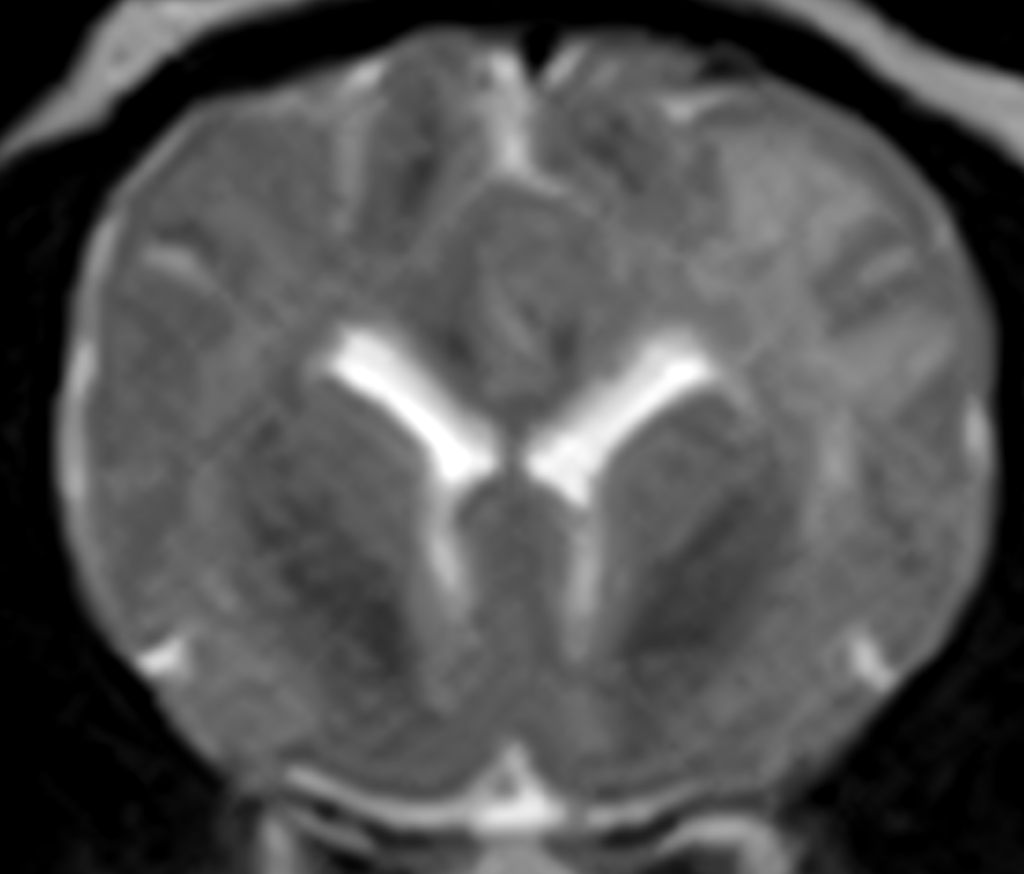
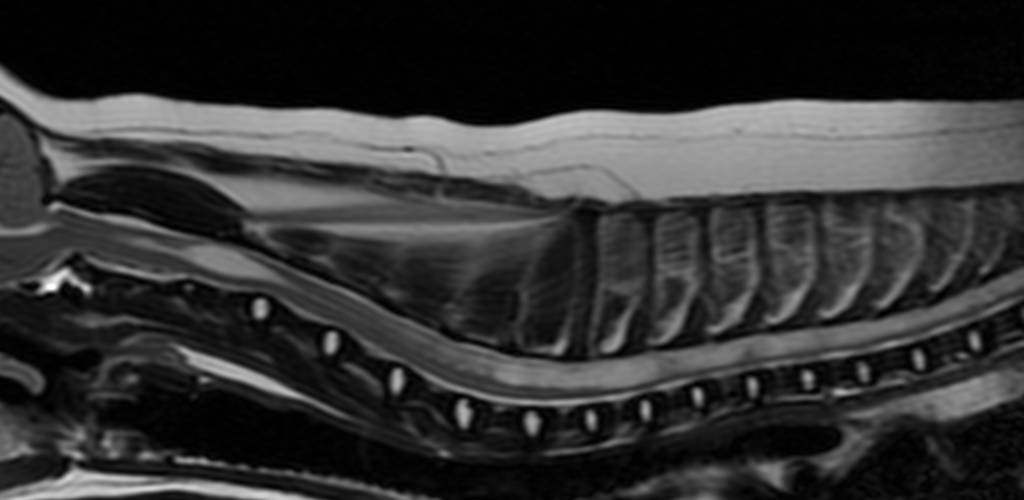
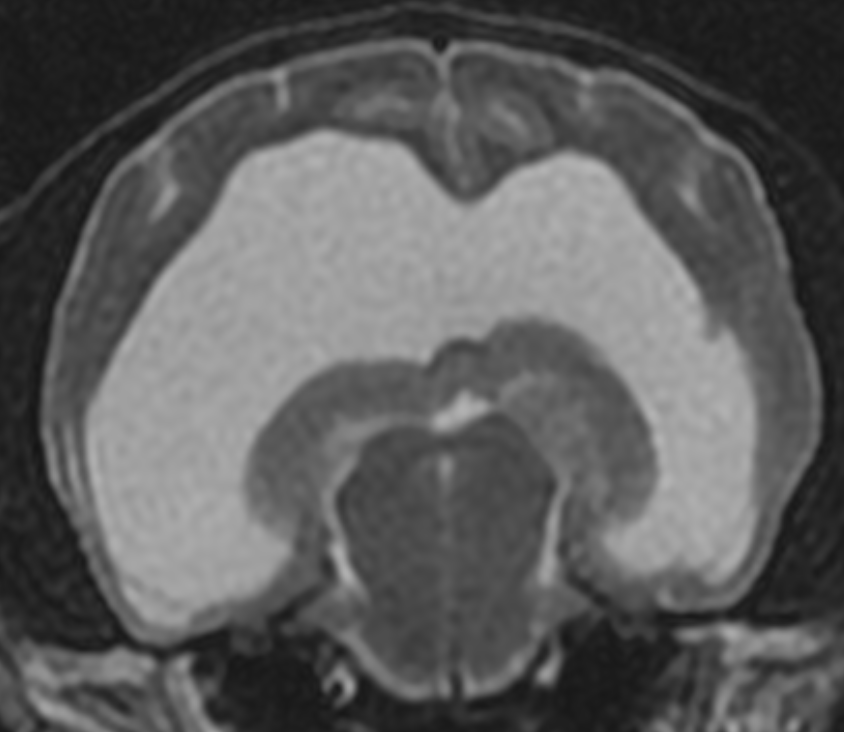

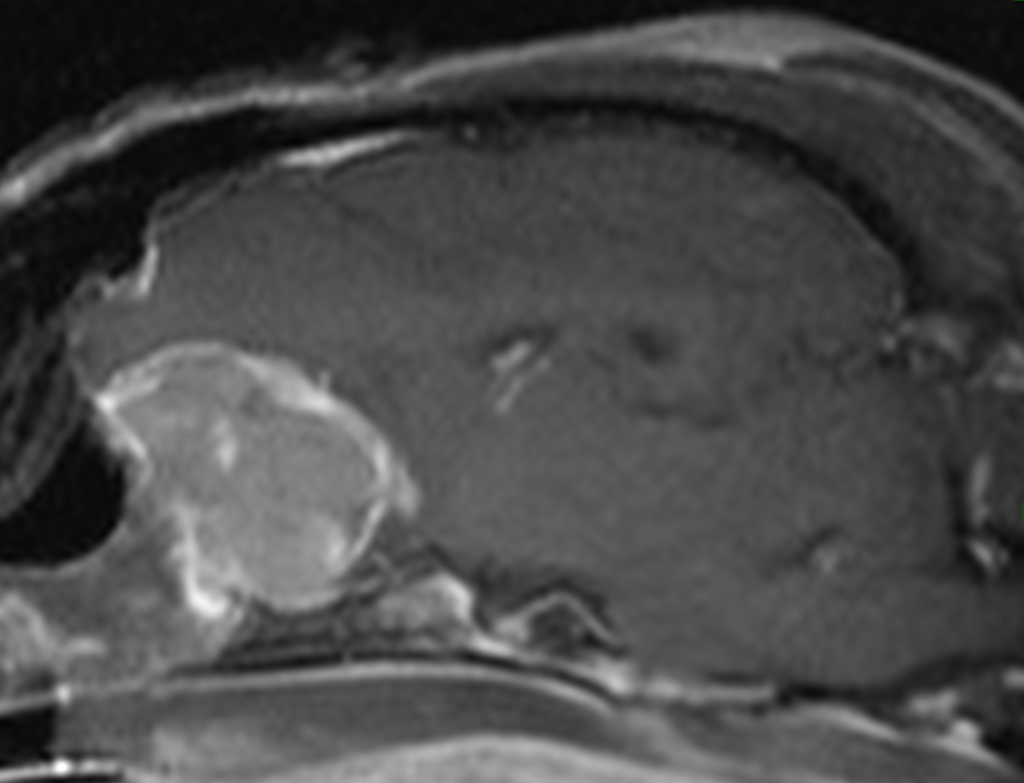



これは複数の研究における猫の鎮痛剤の研究と一致しています。その理由はいくつか考えられますが、主なものの1つとして、人が自分の猫をこのような方法で評価することに慣れていないことが多いということにあります。
本試験とは別に実施したパイロット研究では、プラセボ効果もかなり高かったのですが、飼い主が自分の猫がどんな治療を受けたと思うかを尋ねたところ、プラセボ群の人は約50%の確率で正しかった(プラセボと回答)ことが、注目すべき点のひとつです。
これは確率論からしても50%になり得ます。一方で、治療群では83%の確率で正しい答え(治療群と回答)が返ってきており、より効果を実感できていることがわかります。
今回はプラセボ効果が出やすい長期の試験でしたが、それでもフルネベトマブ群でプラセボ群と比較して有意な改善効果が確認できたことは評価でき、猫の慢性疼痛治療における魅力的な選択肢となると思います。